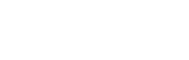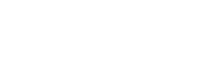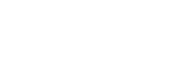女性活躍推進企業の取組事例 (株式会社 山神)
業種:養殖業・食品加工業
株式会社 山神
設立:1993年 本社所在地:青森市大字油川字岡田262-5 従業員数:78人

専務取締役本部長 穐元 美幸さん(左)
常務取締役 八桁 恵美さん(右)
・管理職へのバックアップ体制の拡充
・機械化による身体的負担の軽減
・残業時間の縮減
・女性による新規プロジェクトチームの発足
休むことが許されない時代から
フォロー体制は
部署の垣根を越えて
当社では、仕事にやりがいや楽しさを見出すという視点から、可能性がある限り部署替えを行っています。これは機械的なジョブローテーションではなく、従業員一人ひとりの適性を見極めて判断したり、希望を受けたりすることで決定しているものです。この部署替えが積極的に行われていることで、欠員時にも部署の垣根を越えてフォローできる体制が整えられていきました。
設備投資で働き方が大きく変化
会社設立以来、工場を新設するなどハード面での改革を推進。以前は男性でなければ困難だった作業も、機械化したことで女性も無理なくできるようになり、身体的負担の軽減が実現しました。
それに伴って、作業時間も減り、残業時間を大幅に減らすことに繋がりました。
時代に合わせた働き方へ
管理職登用への打診をする際は、最初は男女共に「自信がない」「管理職に興味がない」という反応が多いように思います。しかし、背中を押してあげていざ管理職へ挑戦してみると、しっかり自分のやるべきことを遂行してくれます。
従業員には「自分には無理だと思っていたことが、やってみたら出来た」という成功体験を積んで、チームをまとめるやりがいや仕事に対する楽しさを見出してほしいですし、そのモチベーション向上こそが企業の成長に繋がると思っています。
従業員の家庭と仕事との両立は、会社全体でバックアップすることを宣言しています。特に女性は家庭における負荷が依然として大きいと思うので、家庭にもしっかり時間を使えるよう企業としてサポートすべきだと考えます。
新たに挑戦し続ける
この事業に対する男性従業員の反応も非常に良好で、秘められたほたての可能性に驚き喜んでくれました。「どんどんやって」と言ってもらえたことも、プロジェクトメンバーの士気向上に繋がっています。
入社して以来やってきた分野とは全く異なる仕事で、違う業界に入ったような気持ちでやりがいがあります。
とても楽しいですし、やってみたいプロジェクトがたくさんあり、挑戦する毎にワクワクします。
女性活躍は表に出ることがすべてではない
入札の場など水産業界の人が集まる場では、女性が表へ出ることを良しとしない雰囲気があります。その中に女性が飛び込んでいっても心ない言葉をかけられたりする現状の中、無理をする必要は全くないと思っています。私たち女性の考えを、社内の男性に託して伝えてもらえばいいのです。「やれる人がやる」。男女で役割分担をしながら、企業にとって最善の選択をしています。
男性が得意としている分野、女性が得意としている分野をミックスさせることで良い効果が生まれるのです。
その中で時間はかかりますが、少しずつ女性の意見も直接聞いてもらえる土台をつくれるよう、社外の人とコミュニケーションを図っています。
国内のみならず海外も見据えて
まるで「日本のもの」であるということに、安心と安全が付属しているようでした。 海外におけるmade in Japan(メイド・イン・ジャパン)への信頼の厚さに、可能性を感じたのです。
危険を伴う漁師という仕事に対して、働いたことへの報酬がもっと魅力的であるべきだと常々感じていますが、国内でほたての価格を大幅に上げることは難しい状況です。
海外は日本よりも物価が高い国が多く、ほたての単価が高くとも受け入れられる点に着目しています。企業成長の面からも、従業員への報酬の面からも、海外への進出は必須といえます。
海外進出プロジェクトに参加している従業員を海外に連れて行き、現地の市場や売り方を自分の目で見ることで、感性を磨いていってほしいと思っています。「やりたい!」「ぜひ行きましょうよ」と言ってくれる従業員がいるから、一丸となって頑張ろうという前向きな雰囲気になっています。
地場産業を100年後まで残すため
企業としての役割
漁師さんが作ったほたてを、海外の人が喜んで食べてくれた話を伝えると「本当に?」と目を輝かせて聞いてくれる。海外での反響を伝えることは、従業員のやる気に直結すると感じています。
今後は日本国内のみならず、海外の人も見てくれるような多角的な情報発信を積極的に行い、その反響を従業員と共有しながら、全体で良いサイクルを作っていきたい。
安心安全で美味しいほたての生産、環境への配慮、従業員のモチベーションUP、海外への可能性の拡大。あらゆる点において妥協せず、挑戦していける企業であり続けたいです。
(令和7年2月取材)