女性活躍推進企業の取組事例(社会福祉法人寿栄会)
業種:福祉業
社会福祉法人寿栄会
設立:昭和61年1月 本社所在地:八戸市大字市川町字夏秋4 従業員数:177人(男性43人/女性134人)

理事長 田名部 厚子さん
・男性の育児休業促進
・職場ぐるみの子育て支援
・職場復帰しやすい環境の整備
・年次有給休暇の積極的な活用促進
・所定外労働削減のための措置
・働きやすい職場環境づくり
・各種資格・認定取得促進などによる人財育成
幹部が積極的に制度を活用し、
「お互い様意識」で休みやすい環境
社会福祉法人寿栄会は、「ご利用者様」「職員」「地域の皆様」との「三方良し」を理念に掲げ、介護サービスを提供しています。
当法人は、元々女性が多く、産休・育休の取りやすい環境づくりは必然と考え取り組んできました。しかし当初は、休むと迷惑がかかるという意識から休みづらい雰囲気があり、制度が上手く生かされていませんでした。そのため、幹部が積極的に制度を活用することで職場全体の意識改革をしました。それにより、「みんなお互い様」という意識が培われ、休みやすい環境になってきていると感じています。
制度利用についての理解を深め
男女とも育休取得率100%達成
根付いたお互い様意識は、育休から復帰する際に「日勤だけ・早番だけしたい」という希望があった場合にも柔軟に対応できています。この意識は女性に限らず職場全体に根付いているため、男女ともに育児休業取得率100%達成や、産後パパ育休(2022年10月施行)の取得に結び付いたと考えています。
職場ぐるみの子育て支援
子連れ・孫連れ出勤OK
復帰した職員が働きやすくなる環境づくりの一つとして、「子連れ・孫連れ出勤制度」を設けています。これは、お子さんの長期間の休みに職場へ連れてくることを許可するもので、今では祖父母も働く時代のため、お孫さんも受け入れています。他にも、親の職場見学や仕事体験ができる「子ども参観日」を行い、職場ぐるみの子育て支援に取り組んでいます。こういった取り組みのおかげもあり、くるみん認定をいただくことができました。
「じゅらちゃん通信」発行
当法人では、職員通信「じゅらちゃん通信」を発行しています。諸制度の周知や「どこの部署の○○さんが出産するよ」「育休から復帰するよ」といった情報を共有することにより、職員同士の理解が進み、みんなでバックアップする体制が自然とできました。
プライベートの充実を図る
「ファミリーサービスデー」を実施
企業理念である「三方良し」の中でも、「職員」が一番大切だと思っています。職員を大切にすることは、職員の生活、家族を守ることにつながります。
毎週木曜日に、残業をしないさせない「ファミリーサービスデー」を実施し、廊下に啓発ポスターを掲示したり、各部署の上司が声がけをするなどして帰宅を促しています。また、年次有給休暇の取得についても、令和2年度は職員平均10日以上という目標を達成することができ、ワーク・ライフ・バランスが取れる環境になってきていると実感しています。
毎月折り紙を作ってくれた職員に理事長賞
当法人では、“よりよい施設になるための案”を募る「提案大会」を開催しています。改善部門の他にも様々な賞があり、トイレや利用者様の食事スペースに毎月季節を感じる折り紙を作ってくれた職員には理事長賞を授与しました。この企画を通して、職員自身が職場の改善点に気づき、環境を変えていく一端となっていくことを期待しています。
課題はコロナ禍からの脱却
今後の課題は、コロナ禍からの脱却です。新型コロナウイルス感染症の影響で施設の休止が相次ぎ、収入が減少しました。さらに、昨今の物価高騰の影響を受けて厳しい状況です。
そして、即戦力となる人材不足です。当法人では、無資格で採用されても働きながら介護サービスに関する資格も取れるシステムを採用しています。外国人雇用を試みようとした時期もありましたが、新型コロナウイルス感染症拡大で入国ができず、泣く泣く断念しました。人材不足により疲弊している施設が他にもたくさんあるのではないでしょうか。
職場で学ぶ場所「寿(ジュ)ライブラリー」
学びができる職場にしたいという思いから当施設の図書館「寿ライブラリー」を設けました。職員、職員のお子さんやお孫さん、地域の方がふらっと立ち寄り、何か1冊の本に出会うきっかけになればと思っています。 また、日本の文化を知って、日本人の誇りや礼節を学んでいただけることを願っています。
無知は無理解を、無理解は憎悪を生みます。恨みがすごく溜まる職場にはしたくないです。だから、まず理解し合って、色々なものを自分たちで作っていける職場を目指しています。
(令和4年12月取材)

1年間の育児休業から戻る時、「じゅらちゃん通信」を見ることにより職場の状況が分かった上で復帰できるため不安が和らぎました。
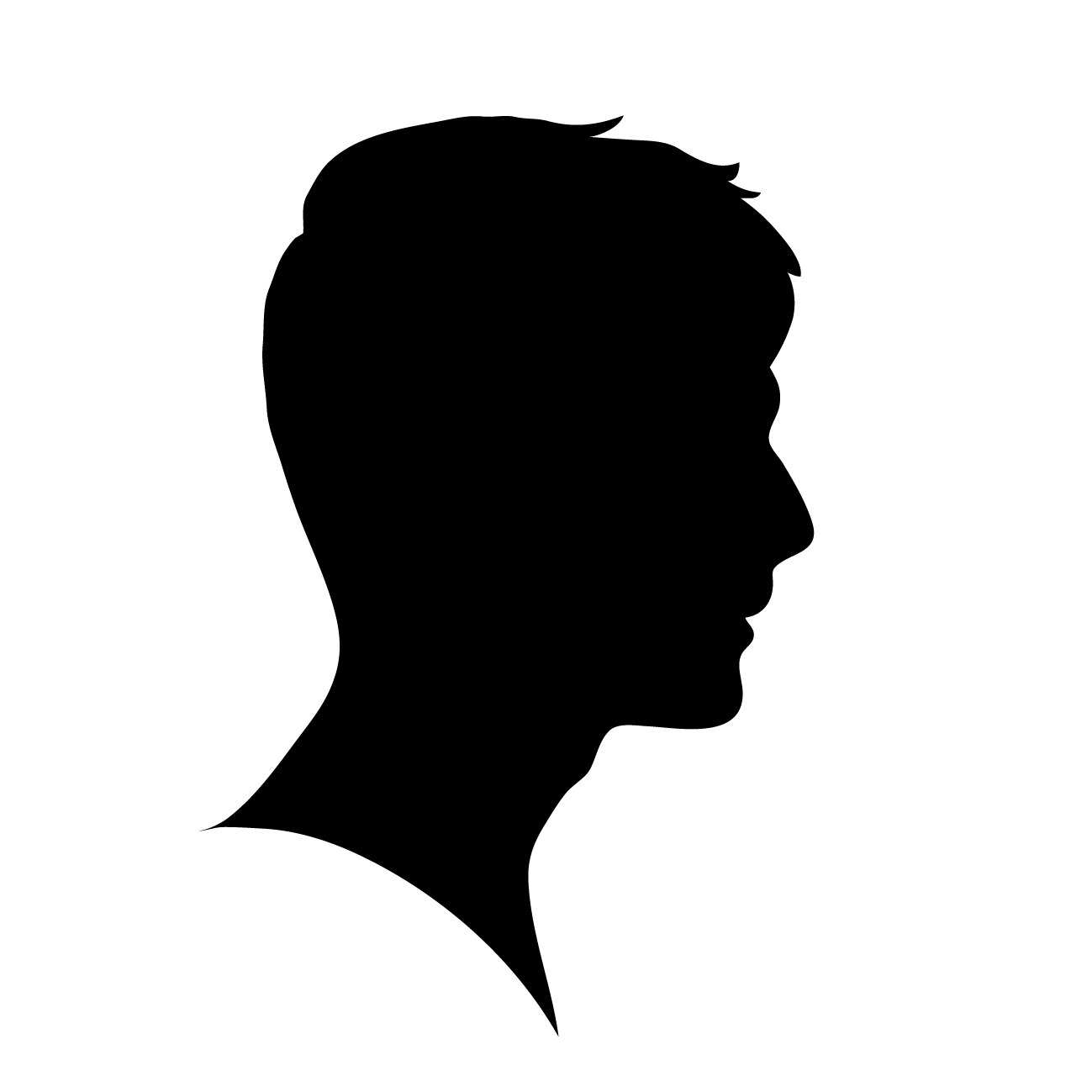
育休を取得する際、先輩からアドバイスやサポートを受けた経験は、他の職員にも気兼ねなく休んでもらえるよう心掛けることに生かされています。


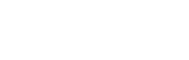
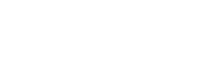

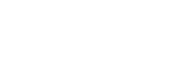
社員コメント