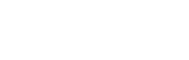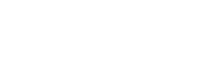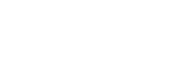青森県女性ロールモデル 【斎藤 美佳子さん】
40歳で起業し、県内外から様々な仕事を受注し活躍する斎藤さん。
斎藤さんの人生や仕事に対する思いについてお聞きしました。
分野:起業

環境にとらわれず、納得のいく道を選んで
斎藤 美佳子さん(弘前市)
北海道生まれ。弘前市在住。
講師、記事執筆、SNS運用、データ分析、オンライン秘書など全国からの仕事を受注するリモートワーカー。
地域情報を発信する「さいとうサポートBlog」にて月間10.5万PVを獲得。
自身の経験から、「ひろさき親と子の不登校ほっとスペース きみだけ」を立ち上げ活動している。
チャレンジのきっかけ
19歳の頃、全国公演で札幌に来ていた劇団『現代座』と出会いました。公演前から約半年の月日をかけて地元の人たちと準備をしていく活動が非常に面白いと感じ、そのまま入団、上京しました。業種や年齢に関係なく地域の人たちをつなぐ現代座の活動に感銘を受けたのです。
地域との結びつきを大切にする劇団の仕事に憧れて入団したものの、人手不足も相まって、自分が出来る仕事は何でもやっていました。本部事務、小道具係、音響スタッフ、地方公演の制作など業務は多岐に渡りました。その頃パソコンがWindowsに切り替わりはじめ、いち早く対応した私が劇団のホームページ(HP)の作成・運営も担っていました。
全体の公演収入が下がるとあっという間に給料が出なくなってしまう小さな劇団での仕事は、非常にタイトです。しかし、私にとっての生きがいでした。収入が無い時はアルバイトをしながら生活をする人もいて、感覚としてはフリーランスに近かったのかもしれないと今になって思います。
☆食べるための仕事×生きがいとしての仕事
弘前市出身の男性と結婚して北海道に戻った後は、劇団の仕事とコールセンターの仕事を掛け持ちしました。普通の会社に入り、働いた時間分のお給料を必ず貰えるという経験をしたときは、とても気持ちが楽だなと感じました。しかし、それはあくまで食べるための仕事。自分がやりたい仕事は、やはり「地域の人たちとみんなで劇場をつくっていく」仕事だったのです。当時は食べていくための仕事と、生きがいとしての仕事を両方やっていたような感覚でした。
その後子どもを授かったタイミングで、子どもを育てるための仕事をする方向へと舵を切り始めました。
☆「さいとうサポート」開業へ
弘前で子育てしたいという夫の思いで、3歳の子どもを連れて弘前に移住。訪問マッサージ治療院の事務補助としてパートタイムで働き始めました。
突如、当初の予定にはなかった医療機関との中間業務もすべて自分がやることに。そこでビジネス支援センターの助言を受け、個人事業主としてサポート事業を開業しました。
それまで自分がフリーランスとして商売をするとは思いもしなかったのですが、当時は「自分がいなければ治療院の先生方は困ってしまうし、何とかしなければいけない。じゃあこれでやってみよう」という気持ちで前に進みました。
チャレンジのみちのり
起業するにあたり、情報発信はとにかく頑張ろうと思いました。そのひとつがブログです。地域の人に自分を知ってもらい、仕事の依頼をもらえるよう地域情報をたくさん発信しました。成り行きで起業したため、マッサージ師の先生方が引退しても自分が廃業しなくていいように枝葉を広げたいという思いもありました。
☆試行錯誤して身につけたスキル
様々な職を経験しましたが、ベースとして「自分で調べて試し、身につける」ということが共通しています。教えてくれる人がいない状況の中では、自分で覚えていかなければならなかったからです。
ITの知識は、劇団でHPを立ち上げる時に自分で調べ、実際に個人のHPを使って試すことで覚えていきました。そのほか機関紙の執筆や編集、Excelの取り扱いなども劇団の中で経験し、必要な場面でその都度覚えていきました。
有名ブロガーのオンラインスクールに入って勉強した際は、とにかく質問したり、先生をつかまえてインタビューして記事を書かせてもらったり。自ら学びに行く場では、活用できるものはたくさん活用しようと行動しました。
☆ブログでのアウトプット
自分で見たものや体験したことは、アウトプットすると自分に定着すると思っています。見たものをもう一回自分の中で解釈して発信することで、自分の中の水はけを良くするイメージです。
それに加えて良い講座やイベントに参加すると、恩返しがしたくなってきます。そのため私はブログでレポートを書いて、参加出来なかった人たちに向けて「こんなに素晴らしい会だったんだよ」と広める方法をとっています。
☆活動のなかで生まれた「つながり」
自分から仕事をとるために営業するのが苦手なのですが、ブログで情報発信する中でつながった縁もあります。
企業が主催するIT系のセミナーなどに受講者として参加した際は、とても細かいレポートを翌日までにブログに掲載することを徹底していました。それが主催者側の目に留まって仕事に繋がったケースはいくつかあり、ブログやWebでの情報発信についての講師を依頼されました。
当初は「わたしでいいのか」と不安がありましたが、現在もその企業に携わることができています。
また、自身のブログでの閲覧数が月間10.5万PV(ページビュー)を突破したことで、様々なメディアから声が掛かりました。新聞に掲載されたり、ブロガーとして記事の執筆を依頼されたり。その後は様々な活動をしているうちに、仕事に繋がるケースが多くなりました。
チャレンジしてみて
私は小学校5年から中学校を卒業するまで、学校に行かなかった経験があり、途中からはフリースクールに入っていました。
そこでは自分で好きなことを見つけて選び、調べていくという事が当たり前。自分の根幹はそのあたりから来ている気がします。「決まった場所に行けば○○が教えられて、○○が身に付く」という経験をしていないからこそ、必要な時に自分で必要な情報を取捨選択して、自分で決めていくことが10代の頃から始まっていたのかなと思います。
☆不登校の親子の会「ほっとスペースきみだけ」
現在、「ひろさき親と子の不登校ほっとスペース きみだけ」を設立し活動しています。
学校に行かなかったから「社会に通用しない」とか、逆に「天才的な起業をする」とか、そういう人ばかりではありません。私のように普通に子育てして仕事をしている人が実はたくさんいるんだということを、現在悩んでいる人に伝えたいなと思っています。
不登校でも「人生詰んだわけではないよ」「大丈夫だよ」ということを伝えていきたくて、不登校の親子の会を作って、同じ立ち位置の人たちとつながりたいのです。
☆人と人とをつなぐ存在として
IT・Webが苦手な方、手が回らない事業者のサポートをしています。村のかかりつけのお医者さんのように、困ったら相談できて、大ごとであれば専門医につなげられるような存在でいたいなと思っています。仕事でも仕事じゃなくても、地域の人と人とをつなぐ役割ができればいいですね。
コロナ禍から仕事の内容が変わり、県外の仕事も多くなっていますが、SNS等での地域の情報発信は現在も続けています。
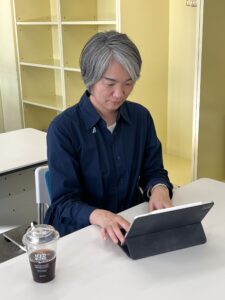
これからチャレンジする女性へのメッセージ
私自身の人生も、何かを選択する場面では安定よりもちょっと面白そうな方を選びがちです。
どうせ人は最後は死んでしまうものなので、楽しいことをして満足できるよう、それまでに納得のいくような道の選び方をしていってほしいです。
(令和6年10月取材)